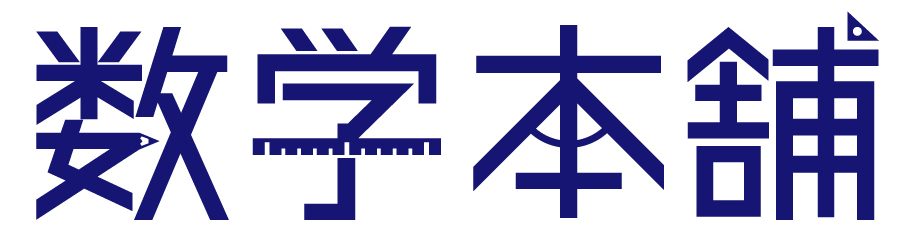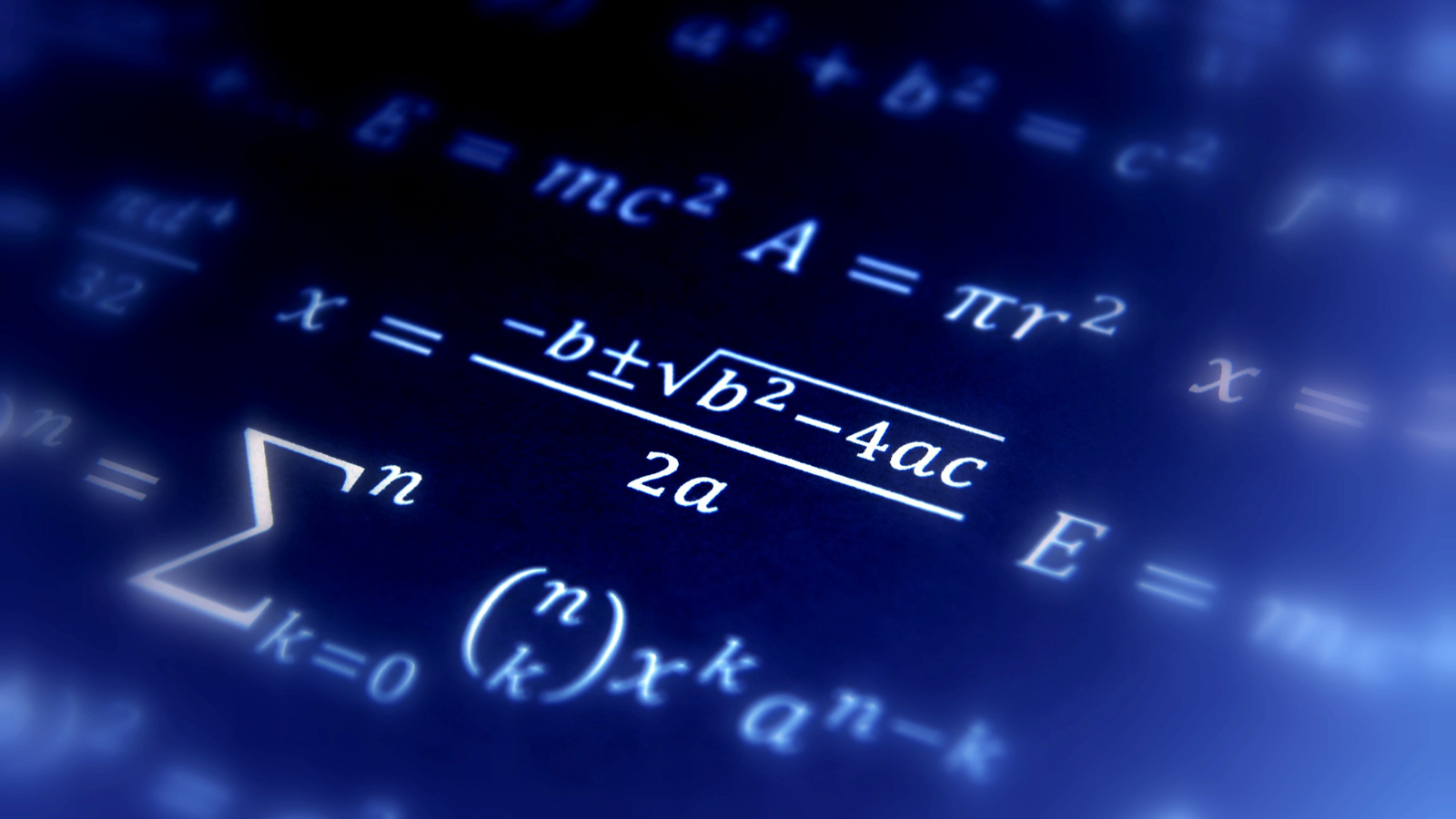角の二等分線定理とは?
辺の比が一瞬でわかる理由
角の二等分線定理:長さは出せなくても“比”なら出せる
三角形の頂点から角をちょうど半分に分ける線(角の二等分線)を引くと、不思議なことに、向かい側の辺が「きれいな比」に分かれます。実はこれ、“長さを全部出さなくても比だけは一発で決まる”という、とても強力な道具なんです。
◆ 今日やること
- 角の二等分線定理(内角・外角)の内容と使い方をつかむ
- なぜ成り立つのかを、面積比のやさしい証明で理解する
- 典型問題の解き方の型と落とし穴を知る
- 次回の チェバ/メネラウス(比の連鎖)へつなげる
◆ 内角の二等分線定理(公式)
\(\triangle ABC\) における \(\angle A\) の二等分線が辺 \(BC\) との交点を\(D\)としたとき、
\[AB:AC=BD:DC\]
言い換えると、「対辺の内分比=角の両隣の辺の比」
逆定理:\(AB:AC=BD:DC\) ならば点 \(D\) を通る直線は \(\angle{A}\) を二等分する
◆ 外角の二等分線定理(公式)
\(\triangle{ABC}\) において \(\angle{A}\) を外側に開いた外角の二等分線が辺 \(BC\) の延長線との交点を\(D\)としたとき、
\[AB:AC=BD:DC\]
言い換えると、「対辺の外分比=角の両隣の辺の比」
* 内角なら内分比、外角なら外分比になる、と覚えると整理しやすいです。
◆ なぜ成り立つ?(面積比で証明)
\(\triangle{ABD}\) と \(\triangle{ACD}\) において
\(\angle{BAD} = \angle{CAD}\) より
\(\triangle{ABD}\)の面積 \(:\triangle{ACD}\)の面積 \(=\left(\frac{1}{2}AB\cdot{AD}\sin{\angle{BAD}}\right):\left( \frac{1}{2}AC\cdot{AD}\sin{\angle{CAD}}\right) = AB : AC\)
一方、 \(\triangle{ABD}\)の面積 と \(\triangle{ACD}\)の面積は同じ高さを共有するので、底辺の比で表せて
\(\triangle{ABD}\)の面積 \( : \triangle{ACD}\)の面積 \( = BD : DC\)
よって、
\[AB:AC=BD:DC\]が言える。
この証明は、内角の場合のものであるが、外角の場合もほぼ同様に示すことができる。
◆ この定理の使いどころ
例題1(基本):比の即決と長さ
\(\triangle{ABC}\) において \(AB=8,\ AC=5. \ \angle{A}\) の二等分線と \(BC\) の交点を D とする.
(1) \(BD:DC\) を求めよ.
(2) \(BC=39\) のとき, \(BD,\ DC\) を求めよ.
解答
(1) \(BD:DC=AB:AC=8:5. \)
(2) \(8:5\) の合計は \(13. \ BC=39\) なので,\(BD=39\times\frac{8}{13}=24, \ DC=39\times\frac{5}{13}=15. \)
例題2(応用):座標での二等分点
三角形の座標が \(B(2,1),\ C(8,4)\),かつ \(AB=5, \ AC=7\) とする.\(\angle{A}\) の二等分線と \(BC\) の交点\(D\) の座標を求めよ.
解答(内分公式)
\(BD:DC=AB:AC=5:7.\)
原点を基準点として,点\(A,\ B,\ C,\ D\) の位置ベクトルをそれぞれ\(\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c},\ \vec{d}\)とすると,
\[\vec{d}=\frac{7\vec{b}+5\vec{c}}{5+7} =\frac{7(2,1)+5(8,4)}{12}=\frac{(14,7)+(40,20)}{12}=\frac{(14+40,7+20)}{12}=\frac{(54,27)}{12} =\left(\frac{9}{2},\ \frac{9}{4}\right).\]
よって、点\(D\)の座標は\(\left(\frac{9}{2},\ \frac{9}{4}\right)\)である.
例題3(外角):外分の扱いに注意
\(\triangle{ABC}\) について,\(\angle{A}\) の外角の二等分線が ,辺 \(BC\) の延長上で \(E\) と交わる.
\(AB=5,\ AC=8,\ BC=9\) のとき,\(BE\) の長さを求めよ.
解答
外角二等分線より,\(BE:EC=AB:AC=5:8\)(外分)。
点\(E\)は点\(B\)の左側にあることから,\(BE=\frac{5}{8-5}\cdot 9=15\)である.
◆ よくある落とし穴
- 対応の取り違え:\(BD:DC=AB:AC\) の“向かい合わせ”を崩さない
- 外角での外分を内分と誤解:外角=外分!
- “二等分線らしき線”の取り違え:中線・垂線・垂直二等分線と混同しない
◆ 歴史の豆知識
ユークリッド『原論』にも通じる古典結果。古代から比は幾何の中心テーマで、角の二等分線定理は“長さを測らずに比を制する”代表選手です。
まとめ ▶▶▶ 角の二等分線定理
- 角の二等分線は、辺の比を一撃で決める:\( BD:DC=AB:AC\)
- 証明は面積比・相似・正弦定理など複数の視点でOK(=強い定理)
- 座標やベクトルの内分公式、外角では外分として使う
- 次回、チェバ/メネラウスで「交点と比」の道具箱をさらに拡張します
📌 数学本舗の無料体験で「定義から理解する数学」を体験してみませんか?
数学本舗では、公式を丸暗記するのではなく、「なぜそうなるのか?」を構造から理解する指導を大切にしています。
図形の“比の道具”を武器にしたい方、無料体験でお待ちしています。
👉 数学本舗 公式サイトはこちら